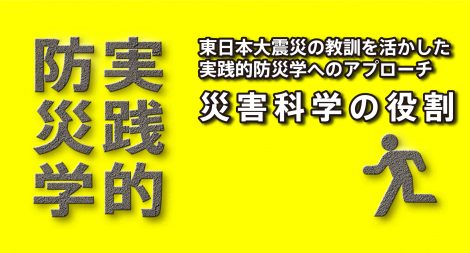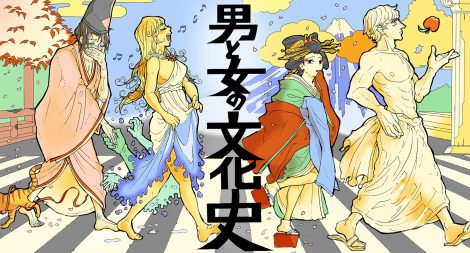東北大学MOOCコンテンツ
東北大学サイエンスシリーズ


東北大学サイエンスシリーズ第10弾
「地震と断層の科学〜日本列島の地震活動を知る」
講師
[災害科学国際研究所] 遠田晋次 教授
開講日:2026年1月21日(水)
募集開始日:2025年11月5日(水)
講座概要
地震発生のメカニズムと日本列島における地震発生場と危険度について、最新の研究成果も交えて科学的に解説します。地震に関する情報やハザードマップを正しく理解する力を養う講座です。
第1週は、最低限知っておくべき地震科学の基礎を話します。地震の防災・減災対策を考えるうえで、地震発生の地学現象を理解しておくことは大切です。なぜ、日本列島で地震が多発するのか、岩盤のズレ(断層運動)がどのように地震の揺れにつながるのか、といった基礎的な解説だけではなく、 1995年阪神・淡路大震災、2011年東日本大震災が、防災だけでなく地震科学の進展における分岐点であったのかについても説明します。
第2週は、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、我々が暮らす陸域直下の浅い場所で発生する地震に注目して解説します。そのような地震の源となる活断層とは何か。どのようにして活断層を見出し、将来の直下型地震の大きさや発生確率を算定するのか。その調査や評価プロセスについて話します。また、熊本地震、能登半島地震、世界の活断層型地震について紹介します。
第3週は、本震とその後の余震、群発地震、続発する大地震など、時空間的にクラスターとなって発生する地震活動のメカニズムを解説します。特に、地震の集団としての統計則、本震や火山活動による周辺地域への応力(歪み)の伝播、地震のトリガリング作用などを、熊本地震や東北地方太平洋沖地震などを例に紹介します。
第4週は、南海トラフ巨大地震、首都直下地震、浅部地殻内地震(活断層型地震)など、今後日本を襲うと考えられている大地震について紹介します。また、今後10年〜30年程度の長期間をみこした地震ハザードマップの作成プロセス、見方、注意点を解説します。大地震への備えへのヒントを提供します。